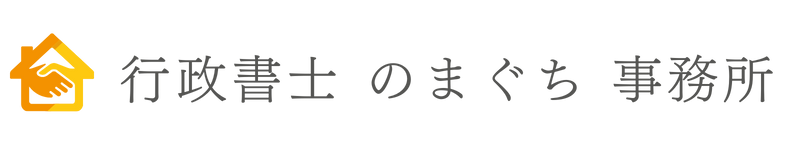相続によって取得した空家を売却する際、一定の条件を満たせば最大3,000万円の譲渡所得控除(空家特例)を受けることが可能です。
本記事では、特に建物登記がされていない「未登記建物」の場合でもこの控除が適用できるのか、またその際に必要となる建築年月日の証明方法について詳しく解説します。
空家相続に適用される3,000万円の特別控除とは
相続した不動産が空家である場合、一定の条件を満たせば、その売却によって得られる譲渡所得から最大3,000万円を控除できる制度があります。これは正式には「被相続人の居住用財産(空家)を売ったときの特例」として、所得税法に定められた特別控除制度です。
この制度は、老朽化した空家の流通促進や防災対策として位置づけられ、適用を受けることで譲渡所得税の大幅な軽減が期待できます。
登記されていない建物でも空家特例は適用可能か?
未登記建物でも制度上の適用は可能
相続した空家が未登記の建物である場合でも、一定の条件を満たしていれば空家特例の適用を受けることができます。制度上、「登記された建物であること」は特例の適用要件とはされていないため、登記の有無は直接の影響を及ぼしません。
つまり、未登記であっても相続した空家が昭和56年5月31日以前に建築され、被相続人が居住していた建物であれば、特例の対象となる可能性があるということです。
空家特例の主な適用要件
この制度を利用するには、以下の要件をすべて満たしている必要があります。
- 相続によって取得した建物であること
- 被相続人が居住していた空家であること(施設入所等による不在は要件を満たす場合あり)
- 建物が昭和56年5月31日以前に建築されたこと
- 建物を耐震改修して売却、または解体して土地を売却すること
- 売却価格が1億円以下であること
- 相続後、譲渡日までに他人に貸与・居住させていないこと
これらを満たせば、最大3,000万円の控除が譲渡所得から適用されます。
未登記建物における建築年月日の証明がポイント
未登記建物で空家特例を利用する際の最大のポイントは、「建築年月日の証明」です。登記された建物であれば、登記事項証明書に建築年月日が記載されているため、それをもって証明が可能です。
しかし未登記建物の場合は、登記簿が存在しないため、他の方法で建築年月日を証明しなければなりません。
建築年月日を証明する具体的な方法
未登記の空家について建築年月日を証明するためには、以下のような資料を利用します。
固定資産税関係書類
- 固定資産税納税通知書:多くの場合、建築年月日または建築年が記載されており、有効な証明資料となります。
- 固定資産税評価証明書:登記の有無に関係なく発行され、建築年が記載されていれば証明書として活用可能です。
- 名寄帳:評価証明書と同様に建築年が確認できることがあります。
これらの書類は、市町村役場の税務課などで取得可能であり、建物の建築時期を第三者的に証明できる資料として評価されます。
その他の補足資料
上記の書類に建築年月日の記載がない場合、以下のような追加資料が必要になります。
- 建築請負契約書
- 建築確認通知書や検査済証(残存している場合)
- 昔の住宅ローン契約書
- 写真資料や自治体からの証明書類など
これらを総合的に提出することで、建築年月日を客観的に示すことが可能となります。
空家相続における未登記建物の注意点
未登記の相続空家で空家特例を活用する際には、以下の点に注意が必要です。
- 建築年月日の証明が必須:これがなければ制度の適用は不可能です。
- 自治体や税務署によって対応が異なる可能性がある:同じ資料でも解釈が異なる場合があり、個別の確認が重要です。
- 建物の解体または耐震性の確保が必要:昭和56年5月31日以前に建てられた建物であれば、多くが旧耐震基準で建築されており、特例適用には追加工事や解体が必要になることがあります。
空家特例を活用するには専門的な対応が不可欠
未登記建物であっても、空家特例を活用できる可能性はありますが、そのためには正確な書類の整備と税制上の知識が求められます。とくに建築年月日の証明や相続人間の手続きの整合性、売却時の手続きには専門的な確認が不可欠です。
適用の可否は最終的に税務署の判断となるため、事前に税理士や不動産の専門家、行政書士などに相談しながら進めることが重要です。誤った申告や不十分な書類提出は、後に特例が否認されるリスクを伴います。
まとめ
未登記の建物であっても、相続によって取得した空家の売却については、「空家特例」による3,000万円の譲渡所得控除を受けることが可能です。重要なのは、建物の建築年月日を第三者的に証明できるかどうかという点であり、特に固定資産税評価証明書などの公的書類が鍵となります。
空家相続は、制度の内容や実務が複雑である一方で、大きな税務メリットを享受できるチャンスでもあります。正確な情報収集と専門家の関与のもと、慎重に手続きを進めることが望まれます。